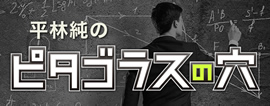日本では、さまざまなものを作るときの「規格」に関する「決まり」があります。
JIS(日本工業規格)と呼ばれるその「規格」には、さまざまなものが満たすべき「決まり」が書かれています。
たとえば、JIS Z 9120~JIS Z 9124といった規格では、野球場・サッカー場・テニス場…といったスポーツ施設に「照明(灯り)の設置方法」についての決まりが定められています。それらJIS規格は、競技場のさまざまな場所の明るさや、照明の向き・光をあてる角度・照明器具の配置などを、こと細かに決めているのです。
 ためしに、「この明るさ(照度)にしなさい」という決まりを、競技場の(一番明るい場所を)明るい順番にトップ5を並べてみると、つまり「明るさ選手権」を開催してみると、こんな具合になります。
ちなみに、プロ野球など向けには、内野や外野…など場所によって「明るさの決まり」は違っています。
(たとえば、プロ野球の外野は”内野よりかなり暗い”1200ルクスと決められています)
ためしに、「この明るさ(照度)にしなさい」という決まりを、競技場の(一番明るい場所を)明るい順番にトップ5を並べてみると、つまり「明るさ選手権」を開催してみると、こんな具合になります。
ちなみに、プロ野球など向けには、内野や外野…など場所によって「明るさの決まり」は違っています。
(たとえば、プロ野球の外野は”内野よりかなり暗い”1200ルクスと決められています)
- 相撲・ボクシング・レスリング(職業試合):3000ルクス
- プロ野球(内野):2000ルクス
- バレーボール(Vリーグ):1500〜1600ルクス
- アマチュアボクシング:1500〜1600ルクス
- スケート(公式競技):1500ルクス
意外に、競技毎に定められた明るさが違っていることに気づかされます。
そして、たとえば素早く至近距離で闘う格闘技に「明るさ」が必要なことなど、何だか「なるほど、確かにそうだよね」と思えるようになるのも、また事実です。
こうした「明るさ」は、競技をするために必要な明るさや、その競技を見やすく眺めるために必要な照明配置などによるものです(たとえば、この競技場の明るさの決まりには、テレビ撮影をする時の明るさの決まりなどもあるのです)。
たとえば、競技の速さや特性…そういったものによって競技場の各場所の「明るさ」が決められています。
私たちの身の回りにあるさまざまなものには、やはりさまざまな「決まり」が作られていて、それらの決まりにもとづいて、多くのものが作られています。
それらの「決まり」は、何かしらの「理由」にもとづいて作られているわけですから、「決まり」の秘密を探っていくと「なるほどな」と思う理由が見えてきます。
JIS規格の「明るさの決まり」では、相撲・ボクシング・レスリングといった格闘技の「舞台」がダントツ明るい、のです。
格闘技の舞台が、JIS(日本工業規格)で定められた「決まり」として、何より一番明るく照明に照らされた「世界」だったのです。
 スカートの長さが32cmよりも長ければ、スカートの内側を見られる心配はありません。
なぜなら、「風が吹くことさえなければ、角度が25度程度の比較的急な階段であったとして、スカートの内側を見ることはできない」ということが数学的に証明されているからです。
たとえば、階段の上に立つミニスカートを履いた女性がいたとしても、そのスカート丈が32cmよりも長ければ、(たとえ、どんなに階段の下に降りてみたとしても)ミニスカートの内部を覗き見ることはできないという代数幾何的な証明がされているのです(参考:ミニスカートの幾何学)。
スカートの長さが32cmよりも長ければ、スカートの内側を見られる心配はありません。
なぜなら、「風が吹くことさえなければ、角度が25度程度の比較的急な階段であったとして、スカートの内側を見ることはできない」ということが数学的に証明されているからです。
たとえば、階段の上に立つミニスカートを履いた女性がいたとしても、そのスカート丈が32cmよりも長ければ、(たとえ、どんなに階段の下に降りてみたとしても)ミニスカートの内部を覗き見ることはできないという代数幾何的な証明がされているのです(参考:ミニスカートの幾何学)。
しかし、32cm丈のスカートで安全なのは、角度が25度程度の階段までに過ぎません。
もしも、それより急な階段があれば、もっと長いスカートを履いていなければスカートの内側が見えてしまう、ということになります。
それでは、一体どのくらいの長さのスカートであれば「スカートの内側を見られる心配をしなくて済む」のでしょうか?
 実は、もしも35cm以上の丈があるスカートであれば、日本国内においては「スカートの中にある下着を覗かれることはない」のです。
なぜかというと、建築基準法 施行令(第三節 第二十三条)によって、公共の場所においては「階段の一段の高さは18cm以下で幅は26cm以上、そして、階段の高さが3m以上であれば、3m以内ごとに1.2m以上の長さの踊り場を設けなければいけない」と決められているからです。
この建築基準法施行令の規定にしたがうと、日本国内で作ることができる「(公共の場所における)最も急な階段」は35度となります。
そして、前述の「ミニスカート幾何学」を用いると、35度の急階段であったとしても(偶然、階段の角度と同じ数値である)35cm丈の長さのスカートであれば、スカート内部の下着を覗かれてしまうことはない、ということも証明されるのです。
つまり、日本国内の公共の場所においては、35cm以上の丈があるスカートを履いている限り、スカートの中にある下着を覗かれることはない、というわけです。
実は、もしも35cm以上の丈があるスカートであれば、日本国内においては「スカートの中にある下着を覗かれることはない」のです。
なぜかというと、建築基準法 施行令(第三節 第二十三条)によって、公共の場所においては「階段の一段の高さは18cm以下で幅は26cm以上、そして、階段の高さが3m以上であれば、3m以内ごとに1.2m以上の長さの踊り場を設けなければいけない」と決められているからです。
この建築基準法施行令の規定にしたがうと、日本国内で作ることができる「(公共の場所における)最も急な階段」は35度となります。
そして、前述の「ミニスカート幾何学」を用いると、35度の急階段であったとしても(偶然、階段の角度と同じ数値である)35cm丈の長さのスカートであれば、スカート内部の下着を覗かれてしまうことはない、ということも証明されるのです。
つまり、日本国内の公共の場所においては、35cm以上の丈があるスカートを履いている限り、スカートの中にある下着を覗かれることはない、というわけです。
足を滑らすと危ない急階段を防ごうという建築基準法施行令の第三節 第二十三条の規定は、滑落の危険を防止するとともに、ミニスカートの安全をも守っているのです。…風が吹かない限りにおいては。
…今回の話は「風が吹いたりすることがなければ」という話です。
しかし、法律書のページをめくり、その中にある数字を科学的に解き明かしていくと、『建築基準法とミニスカートの幾何学による「35cm丈のミニスカートは絶対安全」という証明をすることができる』なんて、何だか少し面白いとは思いませんか?
昔、「○×枚の紙幣から○×枚+1枚の紙幣を作り出してしまう」という禁断の偽札が出回ったことがあります。
それは、
- 何枚もの紙幣を途中で切断し、
- 切断した紙幣を他の紙幣と貼り合わせる
というだけの、とても原始的な方法で作られた偽札でした。
たとえば、下に貼付けた写真では、写真左部に「少しづつ違う位置で切断した(子供銀行発券の)千円札」が並べられています。
そして、切断した千円札の切断右部分をそれぞれ下へ1個づつずらしていくと…なんとビックリ!いつの間にか千円札(子供銀行券ですけどね)が1枚増えています!

この手順を眺め・考えてみれば、「千円札の切断右部分をそれぞれ下へ1個づつずらしていく」ことで、それぞれの千円札の長さが少しづつ短くなっていること、つまり、千円札の面積が少しづつ小さくなっていることに気づくはずです。
それぞれの千円札を少しづつ小さく/切り詰めて、その切り詰めた部分で新たな千円札を1枚作り出す…というわけです。
単純に言ってしまえば、もしも、紙幣の長さが10センチメートルであったなら、紙幣の長さを9.5センチメートルに切断してしまえば、残った5mmの紙幣のカケラを19枚集め・貼り合わせれば、新しくもう1枚の9.5センチメートルの長さの紙幣が生み出される、というような仕組みです。
もちろん、こんな原始的な方法で作られた偽札はすぐ見破られてしまいます。
何しろ、右上の写真は「36枚の千円札から37枚を作り出す」という実験ですが、写真をよくよく眺めてみれば、千円札を小さく切り詰め過ぎて、「1000円札」が「100円札」になっていたりします。
この偽札を人が見たら、何かの冗談かと思うかもしれないような、できの悪さです。
しかも、それだけ完成度が低いにも関わらず、「36枚が37枚に増える」ということは、(工作の苦労は多い割に)たった2パーセントの増率でしかない、というかなりマヌケなテクニックです。
 「紙幣を切断して増やす」のは「偽札作り」として、もちろん禁止されています。
しかし、紙幣が破れたり・破損してしまったりすることがあります。
たとえば、紙幣をポケットに入れたまま洗濯してしまい、紙幣がやぶれてしまった…なんていうこともあるはずです。
そんな時は、一体どうすればいいのでしょうか?
「紙幣を切断して増やす」のは「偽札作り」として、もちろん禁止されています。
しかし、紙幣が破れたり・破損してしまったりすることがあります。
たとえば、紙幣をポケットに入れたまま洗濯してしまい、紙幣がやぶれてしまった…なんていうこともあるはずです。
そんな時は、一体どうすればいいのでしょうか?
紙幣が破損した時には、その紙幣を銀行に持って行けば、残っている紙幣の面積にしたがった金額と交換することができます。
その残っている紙幣の面積にしたがった引き替え額は、次のように決められています。
- 2/3以上:全額
- 2/3未満2/5以上:半額
- 2/5未満:ゼロ円(失効)
また、ここでいう「紙幣の面積」というのは、「同じ一枚の紙幣の一部」と認められる限りにおいて、複数片を合わせた合計の面積で良い、とされています。
ということは、シュレッダーなどで切り刻んでしまった紙幣でも、裁断された破片を集めてくっつけてやれば、(それが同一の紙幣を復元したものだと認められれば)ちゃんとお金と引き替えることができるのです。
 交換基準の2/3と2/5という2つの数字は、もちろん、意味なく決められているものではありません。
全額交換の2/3と半額交換の2/5は、それぞれ6/15と10/15であり、「1枚の紙幣すなわち15/15から全額交換相当の10/15を引くと5/10になり、それは必ず半額交換相当の6/15を下回る」…つまり、全額交換した上にさらに半額交換されることはない、というように決められているのです。
紙幣が破損して困っている人を可能な限り助けつつ、紙幣を切るだけでお金を増やす…なんてことができないように、と考えられているわけです。
交換基準の2/3と2/5という2つの数字は、もちろん、意味なく決められているものではありません。
全額交換の2/3と半額交換の2/5は、それぞれ6/15と10/15であり、「1枚の紙幣すなわち15/15から全額交換相当の10/15を引くと5/10になり、それは必ず半額交換相当の6/15を下回る」…つまり、全額交換した上にさらに半額交換されることはない、というように決められているのです。
紙幣が破損して困っている人を可能な限り助けつつ、紙幣を切るだけでお金を増やす…なんてことができないように、と考えられているわけです。
さて、ここで復習問題です。
上のような交換基準を踏まえて、冒頭で作った「切断千円札」銀行に持ち込んだとしたら、元は36枚の千円札は一体「何枚」になるでしょうか?
- もちろん、元と同じ36枚でしょう?
- 見た目通りの37枚!
- 逮捕状1枚…
 ためしに、「この明るさ(照度)にしなさい」という決まりを、競技場の(一番明るい場所を)明るい順番にトップ5を並べてみると、つまり「明るさ選手権」を開催してみると、こんな具合になります。
ちなみに、プロ野球など向けには、内野や外野…など場所によって「明るさの決まり」は違っています。
(たとえば、プロ野球の外野は”内野よりかなり暗い”1200ルクスと決められています)
ためしに、「この明るさ(照度)にしなさい」という決まりを、競技場の(一番明るい場所を)明るい順番にトップ5を並べてみると、つまり「明るさ選手権」を開催してみると、こんな具合になります。
ちなみに、プロ野球など向けには、内野や外野…など場所によって「明るさの決まり」は違っています。
(たとえば、プロ野球の外野は”内野よりかなり暗い”1200ルクスと決められています)

 実は、もしも35cm以上の丈があるスカートであれば、日本国内においては「スカートの中にある下着を覗かれることはない」のです。
なぜかというと、建築基準法 施行令(第三節 第二十三条)によって、公共の場所においては「階段の一段の高さは18cm以下で幅は26cm以上、そして、階段の高さが3m以上であれば、3m以内ごとに1.2m以上の長さの踊り場を設けなければいけない」と決められているからです。
この建築基準法施行令の規定にしたがうと、日本国内で作ることができる「(公共の場所における)最も急な階段」は35度となります。
そして、前述の「ミニスカート幾何学」を用いると、35度の急階段であったとしても(偶然、階段の角度と同じ数値である)35cm丈の長さのスカートであれば、スカート内部の下着を覗かれてしまうことはない、ということも証明されるのです。
つまり、日本国内の公共の場所においては、35cm以上の丈があるスカートを履いている限り、スカートの中にある下着を覗かれることはない、というわけです。
実は、もしも35cm以上の丈があるスカートであれば、日本国内においては「スカートの中にある下着を覗かれることはない」のです。
なぜかというと、建築基準法 施行令(第三節 第二十三条)によって、公共の場所においては「階段の一段の高さは18cm以下で幅は26cm以上、そして、階段の高さが3m以上であれば、3m以内ごとに1.2m以上の長さの踊り場を設けなければいけない」と決められているからです。
この建築基準法施行令の規定にしたがうと、日本国内で作ることができる「(公共の場所における)最も急な階段」は35度となります。
そして、前述の「ミニスカート幾何学」を用いると、35度の急階段であったとしても(偶然、階段の角度と同じ数値である)35cm丈の長さのスカートであれば、スカート内部の下着を覗かれてしまうことはない、ということも証明されるのです。
つまり、日本国内の公共の場所においては、35cm以上の丈があるスカートを履いている限り、スカートの中にある下着を覗かれることはない、というわけです。