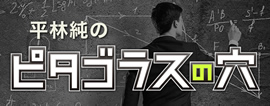無味乾燥に思える「決まり」も、よく眺めてみれば、それは意外に新鮮で面白いものです。
…というわけで、今日は「ガリガリ君」を食べつつ、ちょっと(夏の暑さを吹き飛ばし)涼しい心地を感じることができる「雑学」です。
気象庁の「降水」に関する用語解説ページを眺めると、
- あられ(霰):雲から落下する白色不透明・半透明または透明な氷の粒で、直径が5mm未満のもの
- ひょう(雹):積乱雲から降る直径5mm以上の氷塊
と書いてあります。
この解説を読むと、「霰(あられ)と雹(ひょう)が大きさ(直径5mm)で分けられていた」ということを意外に新鮮に感じるのと同時に、「おや?あられ(霰)は”雲から落下する”と書いてあるのに、なぜ”ひょう(雹)は積乱雲から降る”と雲を積乱雲に限定してあるんだろう?」という疑問を抱くのではないでしょうか?
もちろん、(直径5mm以上という)大きな「雹(ひょう)」を降らす雲が積乱雲、つまり入道雲とか雷雲と呼ばれる雲に限定されているのには理由(ワケ)があります。
入道雲のような強い上昇気流を伴う雲でなければ、直径5mm以上もの大きな「氷の塊」を作り出し、地上に降らすことができないのです。

空から氷片(や水滴)が降るとき、その粒径で(重さに対する)空気抵抗が決まり「地上に落下するまでの時間」が決まります。
粒径が大きいと(氷片の重さに対する)空気抵抗は小さく、上空から単純に氷片が落ちてくるとすると、雲の高さから数分もしないうちに地上に辿り着いてしまう、ということになります。
しかし、そんな短時間に、大きな氷塊を量産できるわけもありません。
「冷蔵庫で直径5mmの氷塊をザクザク・ガリガリと作ろうとしてもすぐに作ることなんてできない」のと同じく、直径5mm以上の大きな雹(ひょう)を作るには、やはりそれなりの時間がかかるのです。
実は、直径5mm以上の大きな雹(ひょう)は「入道雲の中に流れる強い上昇気流に上に吹き上げられることで、入道雲の中に長い時間浮かび続け、長い時間にわたり浮かび続けている間に大きな氷の塊にまで成長し、そして地上に「直径5mm以上の氷塊」となって落ちてくるのです。
だから、サイズが大きな氷塊=雹(ひょう)を作り出すことができるのは強い上昇気流を伴う雲、すなわち、入道雲(積乱雲・雷雲)に限定される、というわけです。

というわけで、雹(ひょう)が降るのは入道雲が空に浮かぶのと同じ季節です。
もっとも、真夏だと、入道雲が空から雹(ひょう)を降らしたとしても、雲の高さから地上へと辿り着くまでの間に「氷片が雨に変わって」しまいますから、だから、雹(ひょう)が降るのは初夏が多くなります。
もしも、この暑い夏に、「シッポ」を伸ばしている真夏の入道雲を見ることができたら、その「シッポ」は実は雲が降らす天然のカキ氷…雹(ひょう)だったりするかもしれません。
そんな時は、「入道雲から伸びるシッポ」の中に入ってみると、ヒンヤリ冷え冷えな雹(ひょう)や霰(あられ)を味わうことができるかもしれません。

京都にある古くからの家の作り、京町家には「居住スペース」の両側に庭があり、その片側の庭にだけ打ち水をすると、暑いままの庭に上昇気流が発生し、水を打った冷やされた庭から涼しい風が座敷を貫通し流れていく、という話があります。
古くから続く京都の町家は、まさにウナギの寝床のようで、入り口から最奥部の坪庭まで部屋と通路が真っ直ぐ続きます。居住空間を囲む両側に、交互に水を撒くことで(水を撒いた側の)地面とその上にある空気を冷やすだけでなく、温度差を作り・空気の密度差を作り、結果として、家の中を心地良く吹く風の流れを作る…というのです。
京町家模型で確かめる打ち水の科学

ためしに京町屋の中にある「庭」に水を撒いたとき、家の中を吹き抜ける風の動きを試算してみると、およそ秒速0.5メートルくらいの「かすかな風」が吹きそう、というようになります。
坪庭は高い壁に覆われています。その壁の高さは4mとしましょう。そして、水を撒くことで、(高さ4mの)坪庭内の気温が2度(外気より)下がったものとします。少しひんやりした坪庭は、坪庭最下部横から(居住空間を介して)暑い外へと空気が通り抜けることができるとします。すると、坪庭内と外部との圧力差で生じる風速はおよそ0.5m/s強、となります。
「打ち水で京町屋を通り抜ける風の速さ」を計算しよう!
しかし、水を撒く場所を、「(壁に囲まれた)家にある中庭」でなく「家の前の路地」に巻いたような場合、冷えた重い空気は家の中に吹き込むことなく、ただ通りに沿って他の場所に流れてしまいます。
そこで、もう一度「京町家模型で確かめる打ち水の科学」で引用した文章を読み直してみると、「居室空間の両側に庭があることが、打ち水には大切な要件だ」と書いてあります。なるほど、水を撒くのは、家の前の路地ではなく、居住空間を挟む「(高い壁に囲まれた)庭」だった、というわけで、この「打ち水のキマリ」とても納得できる話です。
京町家では居室空間の両側に庭がある。そのことが打ち水には大切な要件だと、ご夫妻(西陣帯地「渡文」当主渡邉夫妻のこと)にお教え頂いた。
京町家模型で確かめる打ち水の科学

ところで、2つの庭の温度差が生む気圧差によって風を生じさせようとしたならば、「交互に水を撒く」のではなく、いつも片側の庭を「(外気と同じ)灼熱状態」のままにして、もう片側の庭だけを打ち水で冷やしていた方が効率が良いような気もします。ふたつの庭の間を吹き抜ける風の速さは、(その瞬間に気化熱で冷却される熱量ではなく)庭の温度差に依存しますから、交互に冷やしたりせず「熱い」「冷たい」の機能を分離した方が(生じさせる風速に関しては)効率が良くなりそうです。
…さてさて、暑い夏が「夏真っ盛り」でスタートしました。夏休みの自由研究に「打ち水の科学」を選んで実験・解析をして、あなたの部屋や、あなたの家の前を、あるいは、あなたが暮らす街をちょっと涼しくしてみるのはいかがでしょうか?
ビールをグラスに注ぐと、「グラスの中の泡は上に浮かび上がっていく」のが普通…と思えます。
泡(気体)はビール(液体)より軽いはずだから、そんな現象起きるわけがない!と思うかもしれませんが、
しかし、たとえばギネスビールは、グラスに注いでからしばらくの間、グラスの中で泡が下へ下へと沈んでいくさまが見えます
(この現象は「ギネス・カスケード(垂れ連なる流れ)」と呼ばれます)。
そしてまた、ギネス以外のビールや水ですら、そういった「下に沈んでいく泡」を見ることができます(参考)。

グラスの中で「下に沈む泡」ができるのは次のような理由(過程)によるものです(参考解説・参考数値シミュレーション論文)。
- グラスの中央下部で泡が発生する
- 泡がグラス中央部で上昇する際に、(ビールの)粘性によりビール自体にも上昇流が発生する
- 上昇したビールは、グラス径が広がり始める部分で渦が発生し、(グラス径が広がる部分では)グラス表面に沿って下へ下降する流れが生じる
- (泡が小さい場合)泡に働く浮力はビールの粘性による抵抗力より小さいため、グラス表面近くの下降流に沿って泡が下降していく
これらのことは、少し想像してみると「いたって当たり前」の現象であることがわかると思います。たくさん泡が真上に上っていけば、理想的にサラサラでない飲み物ならば、飲み物自体にも流れが発生するし、(泡が真上に上っていくのに)グラス径が広がれば、飲み物とグラス表面近くには、飲み物の下降流が自然に発生するはずです。…つまり、それはギネスビールに限らず、「(グラス下部で)泡が発生する液体」を「上が広がったグラス」に注げば、実は普通に起きる現象なのです。

「沈む泡」と言えばギネスビール…となる理由は、ギネスビールでは比較的小さな泡ができやすかったり、色が非常に濃くグラス内部の上昇流(と上っていく泡)が見えず・グラス表面近くの下降する泡しか見えないために、ギネスビールでは「下に落ちていく泡」が顕著に目立つから、というわけです。(右の図はグラス内部の流速と泡とビールの比率~茶色部分が泡が多い部分~を示した数値計算結果です)
(ギネスでなくとも)ビールを「上が広がったグラス」に注げば、ギネスビール風「下に沈む泡」を作ることができます。
「上広がりのグラス」を使い、(グラスの上部が絞られている部分にはビールを注がないようにすれば)グラスの径が変わる辺りから上の部分では、泡が下に流れ落ちていくようすを見ることができます。
こんな『ギネスビール風「下に沈む泡」を作るコツ』を覚えておけば、暑い夏を冷たいビールで気持ち良く・楽しく過ごすことができるかもしれません。